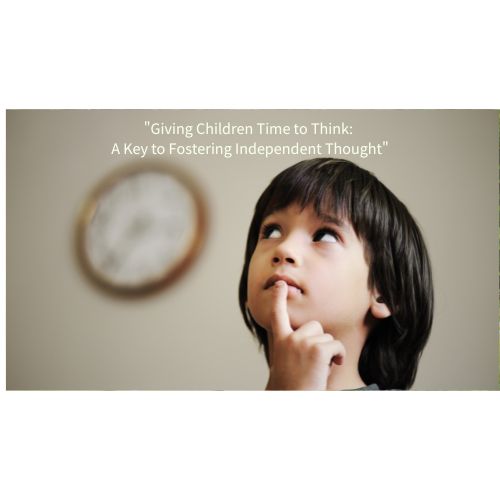子どもが何か困っているとき、すぐに助けてあげたくなるのが親心です。
しかし、子どもが自分で考え、解決する力を養うには、少し立ち止まって「待つ」ことが重要です。
この「待つ力」を身につけることは、親子関係を深め、子どもが自主的に成長するための第一歩となります。
今回は、「待つこと」で子どもの考える力を引き出す方法について具体的に解説します。
1. 考える力を育てるための「待つ」姿勢
子どもが質問してきたとき、すぐに答えるのではなく、少しの時間をあえて置いてみることが、思考力を伸ばすきっかけになります。
例えば「どう思う?」と問いかけることで、子どもが自分なりの答えを考えるチャンスが生まれます。
この小さな「待ち」は、子どもが「自分で考えることができる」という自信を持つうえで、とても大切です。
2. 親の焦りを抑える「待つ力」
子どもがすぐに答えを出さなかったり、失敗を繰り返したりすると、つい口を出したくなることもあります。
しかし、親が焦って先に指示を与えてしまうと、子どもの考える力や自立心を削いでしまうことになります。
たとえば、宿題のやり方が分からずに悩んでいるときも、手を出さずに見守ることで、子どもが自分なりに試行錯誤する時間を持てるのです。
3. 実践例:宿題での思考力の引き出し
宿題に取り組んでいる際、わからない問題が出てきたときに、親がすぐに解き方を教えるのではなく、「どうしてそのやり方を選んだの?」と尋ねてみましょう。
子どもは自分で考えることで、答えを見つける過程そのものから新しい発見を得られます。
たとえ間違っていても、その失敗も大切な学びです。
考えを引き出す質問をすることで、子どもが「考える楽しさ」に触れる機会を増やせます。
4. 子どもの自己肯定感を育む「待ち」
子どもが試行錯誤を通じて自分の答えを見つける経験を積むことで、自然と自己肯定感が高まります。
親がすぐに答えを教えずに見守ることで、子どもは「自分の力で解決できた」という達成感を得られます。
このようにして、子どもは「自分もやればできるんだ」という感覚を育むことができるのです。
5. 「失敗すること」の大切さを理解する
子どもがチャレンジする場面では、たとえ失敗しても、それを責めるのではなく「どこを直したらうまくいくか」を一緒に考える姿勢が重要です。
失敗を恐れず挑戦することで、子どもは実際に解決策を見つけ出せる力を徐々に身につけます。
この待ち方の実践は、親にとっても忍耐が試されますが、子どもが自分自身を肯定する力を育むために欠かせないプロセスです。
6. 信頼の土台を築く「待ち」
親が信頼して待っていることを感じられると、子どもは「自分は認められている」と実感します。
その信頼が、さらに子どもの自己信頼感を高める土台となり、さまざまな場面で「自分でやってみよう」とする意欲を生み出します。
「考える時間がある」というだけで、子どもはのびのびと自由に発想できるようになるのです。
「待つこと」は、ただじっと見守るだけではなく、子どもが考える力を育むための積極的な関わり方です。
親が焦らずに子どもの考えを引き出し、失敗も受け入れて見守る姿勢が、子どもにとって大きな支えとなります。
次回は、さらに「待つこと」で深まる親子の信頼関係について掘り下げていきます。
どうぞお楽しみに!